トトオです。
今回の「好きなんなんなん」は、エマーソン・レイク・アンド・パーマー(以下、ELP)の『ブラック・ムーン』です。
前回の記事はこちら。
今回の記事のポイントはこちらです。
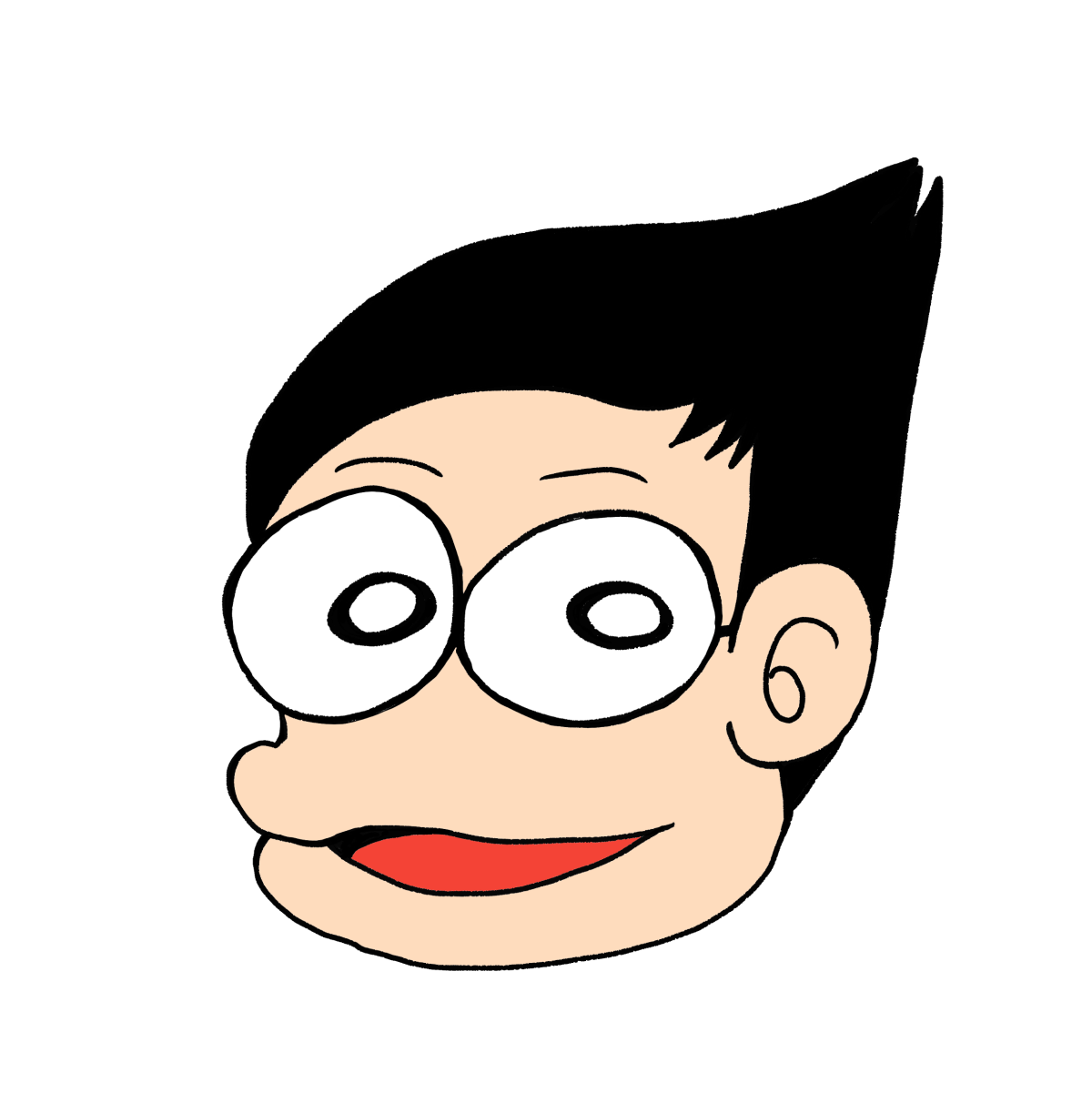
ポイント
最強トリオ、奇跡の再会
結論
先に結論です。
では、レビュー行きましょう。
ELPとそのキャリア
史上最強のトリオは?
以前、ポリスの記事を書いた時に、「史上最強のトリオはポリス」だとほぼ断言しました。
しかし、正確には、「最強のトリオの一つがポリス」という感じでしたね。
今回の記事を書くにあたって、そういえばELPを忘れてたな、とちょっと後悔しました。
(これを言い出すと、他にも色々出てきそうですが・・・)
ELPの最高傑作は?
私がELPを聴き始めたきっかけは、ハードロック名盤カタログで紹介されていたからです。
ギターレストリオですが、『恐怖の頭脳改革』はハードロック的に聴ける名盤なので、色々なガイドブックで見かけました。
いやー、これはよく聴きました。
ELPの最高傑作は、色々な意見があると思いますが、曲単位だと『タルカス』で、アルバムだとやはり『頭脳改革』でしょうか。
いわゆるELPの名盤は、全部70年代の作品です。
彼らは80年代以降グループとしての活動を停止しますが、90年代に奇跡的に復活して、二作のオリジナルアルバムを発表します。
今回紹介する『ブラック・ムーン』は、そのうちの一作目です。
EL&P『Black Moon』(1992)
モダンプログレのメタル化
本作のタイトルトラックは『Black Moon』です。
この曲で顕著なように、本作は「ELP meets Metal」とでも言うような、当時の流行を反映させたプログレメタル的な作風です。
ちなみに、プログレバンドがモダン化するとメタル度が高まるという傾向は、他にも見受けられます。
本作における最大のポイントは、リズム隊によるグルーヴです。
スロー且つヘヴィで、過去のELPとは一線を画す音質です。特にスネアが強烈です。
好き嫌い分かれるところかと思いますが、本作でしか味わえないサウンドという意味では、存在価値はあります。
円熟味を増すパフォーマンス
本作発表当時、三人はすでに40代です。
名実ともにプログレ界の頂点だった70年当時から、20年ほど経過しています。
ビデオを見れば、はっきりと加齢が感じられます(特にグレッグ)。
本作には二十代の時の、彼らの尖ったプレイはありません。
しかし、歳を重ねたことで、それぞれのパフォーマンスに円熟味が増しています。
特筆すべきはグレッグのボーカルで、(体型は変わっても)衰え知らずの素晴らしい歌声は、本作最大の見どころと言えます。
浅草橋ヤング洋品店と中華鍋
本作のハイライトは、中盤の『Changing States』です。
変拍子のインパクトが強いインスト曲ですが、メインの鍵盤のメロディが抜群に格好良く、エネルギッシュな演奏も相まって、聴くと元気の出る一曲です。
私はこの曲を聴くと、ある人を思い出します。
そう(?)、金萬福です。
90年代に「浅草橋ヤング洋品店」というバラエティ番組がありました。
その中に、中華料理人が対決する人気コーナーがあり、この楽曲が使われていました。
そして、そこで最も異彩を放っていたのが、金萬福でした。
私はこの楽曲を聴くたび、カタコトの日本語を話しながら、中華鍋を振り回し暴れまくる金萬福を思い出して、なぜか切ない気持ちになります。
今も元気そうで良かったです。江頭グランブルーとかありましたね~。
(ELPの記事であることを忘れそうです)
手堅いが、総じて「地味」
本作は、前半から中盤にかけて、いくつかハイライトとなる楽曲が配置されています。
しかし、過去のELPの作品にはあった「コレ」といった目玉的な楽曲がありません。
こういう、「コレ」という感じの曲です。
そして、本作は後半にかけて、さらに楽曲が地味になっていきます。
落ち着いた作風で、丁寧に作られているので、腰を据えて聴くと、しみじみ良い(ピアノソロの『Close to Home』なんか名曲)のですが、過去のエキセントリックなELPの楽曲とのギャップは正直大きいです。
本作発表当時の評価は芳しくなく、次作の『In the Hot Seat』は本作よりさらに地味な作風となっていて、汚名挽回には至らなかったようです。
トトオのオススメ名曲ランキング
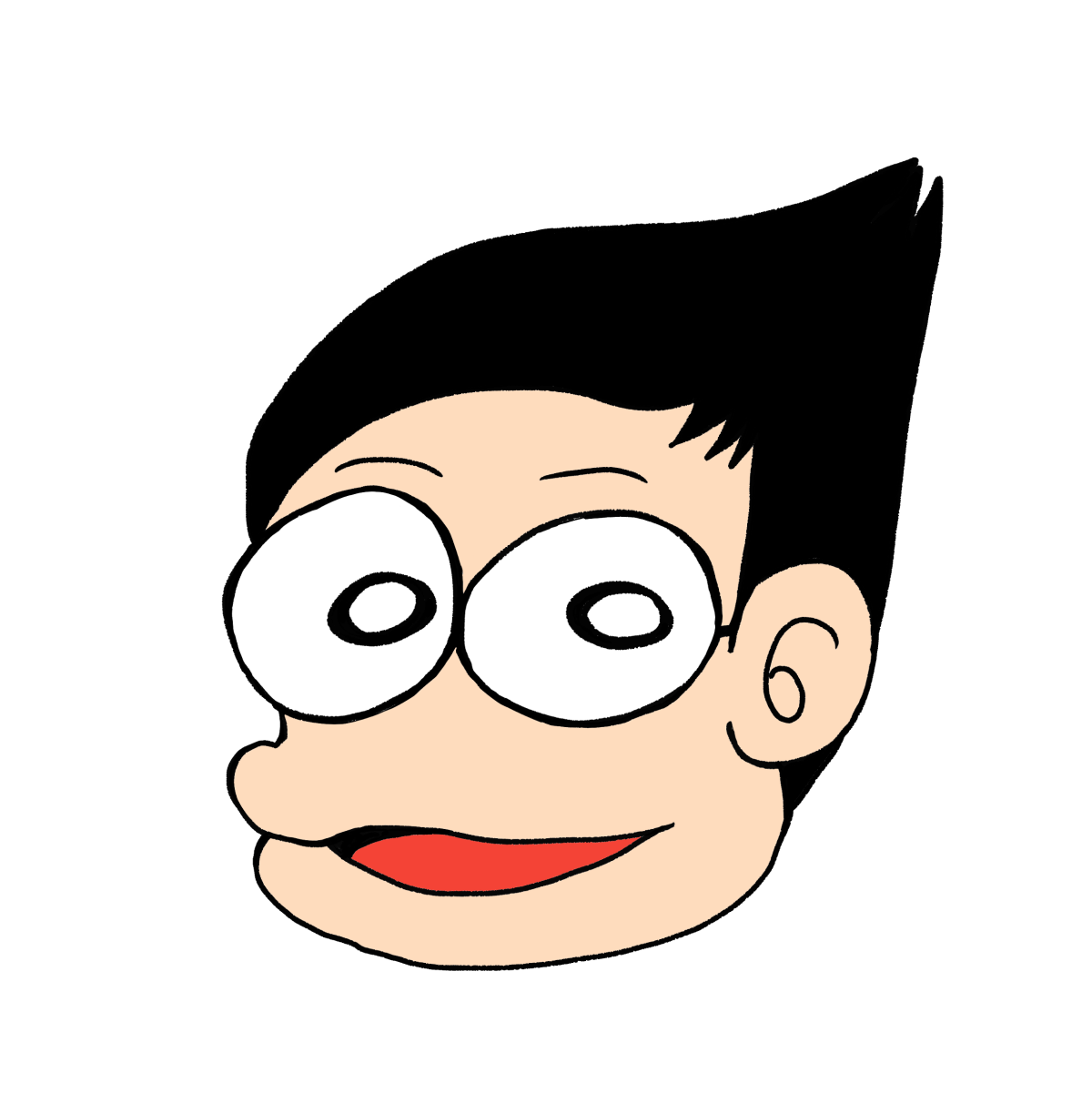
オススメ
ランキング
1位『Black Moon』
2位『Changing States』
3位『Close to Home』
終わりに
すでに、カール・パーマー以外の二人、キース・エマーソンとグレッグ・レイクは亡くなってしまいました。
改めてELPのキャリアを振り返ると、決して順風満帆ではなかったようです。
そんな彼らが、晩年にオリジナルアルバムを発表したという奇跡を、ファンだけが楽しむのはあまりにももったいないです。

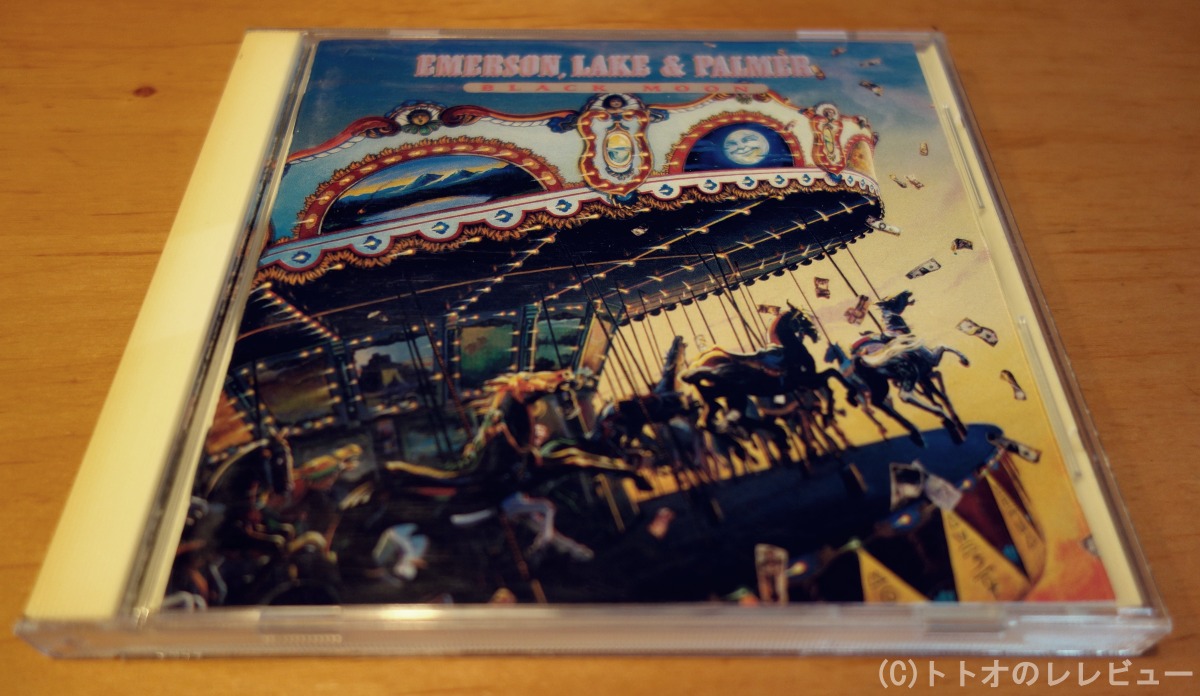



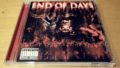
コメント